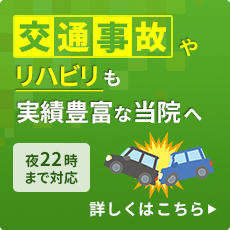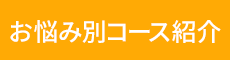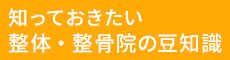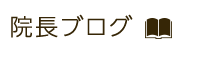1) 使える保険の全体像を把握する
-
自賠責保険(強制保険):ケガ・死亡・後遺障害の“最低限”を補償。傷害は被害者1名につき上限120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級により75万~4,000万円など。まずここから支払われます。
-
任意保険(加害者側):対人賠償・対物賠償で相手の損害、人身傷害で自分と同乗者、搭乗者傷害・無保険車傷害・車両保険・弁護士費用特約などで不足分をカバーします。人身傷害は実損てん補/搭乗者傷害は定額払い、という違いが基本です。
2) 事故直後~保険連絡・受診・支払いの入り口
-
警察へ届出→診断書で人身事故扱いに(ここが補償の起点)。
-
自分の(または相手の)保険会社に事故報告。加害者側の任意保険があると、病院宛の一括対応が始まり、治療費の窓口清算がスムーズです。
-
任意保険が使えない/相手が無保険などの場合は、加害者加入の自賠責へ被害者請求や、当座資金の仮渡金制度が使えます。
3) 何がどこまで補償される?
-
自賠責の主な対象:治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料(傷害は上限120万円内で計算)。不足する分を任意保険(対人・人身傷害など)で上乗せ。
-
参考:自賠責の入通院慰謝料は原則日額4,300円で、「治療期間の全日数」か「実通院日数×2」の少ない方を採用します(傷害120万円の枠内)。
4) 症状が長引く・後遺障害が疑われるとき
-
医師と相談して症状固定→後遺障害等級認定を申請(「事前認定」or「被害者請求」)。
-
書類は保険会社から**損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)**に送られて審査→結果に応じて後遺障害慰謝料・逸失利益等が算定されます。
5) 示談・時効・行き詰まったら
-
損害賠償請求権の時効(加害者に対して):
-
人身損害は5年(2020年4月1日以降適用)、物損は3年が目安。 兵庫県弁護士会
-
-
保険金請求の時効(自賠責・任意):多くは3年(被害者請求は通常事故日の翌日から3年など)。迷ったら早めに請求・時効対応を。
-
交渉が難航する・金額に納得できないときは、弁護士費用特約の利用や、**交通事故紛争処理センター(無料)**での相談・和解あっ旋も有力です。
ひとことアドバイス
-
受診は整形外科を軸に。領収書・通院交通費・仕事の欠勤記録は全て保存。
-
相手保険からの提案はそのままサインせず、診断・資料が出そろってから比較検討。
-
等級認定や示談で迷ったら、早めに専門機関や弁護士へ相談を。